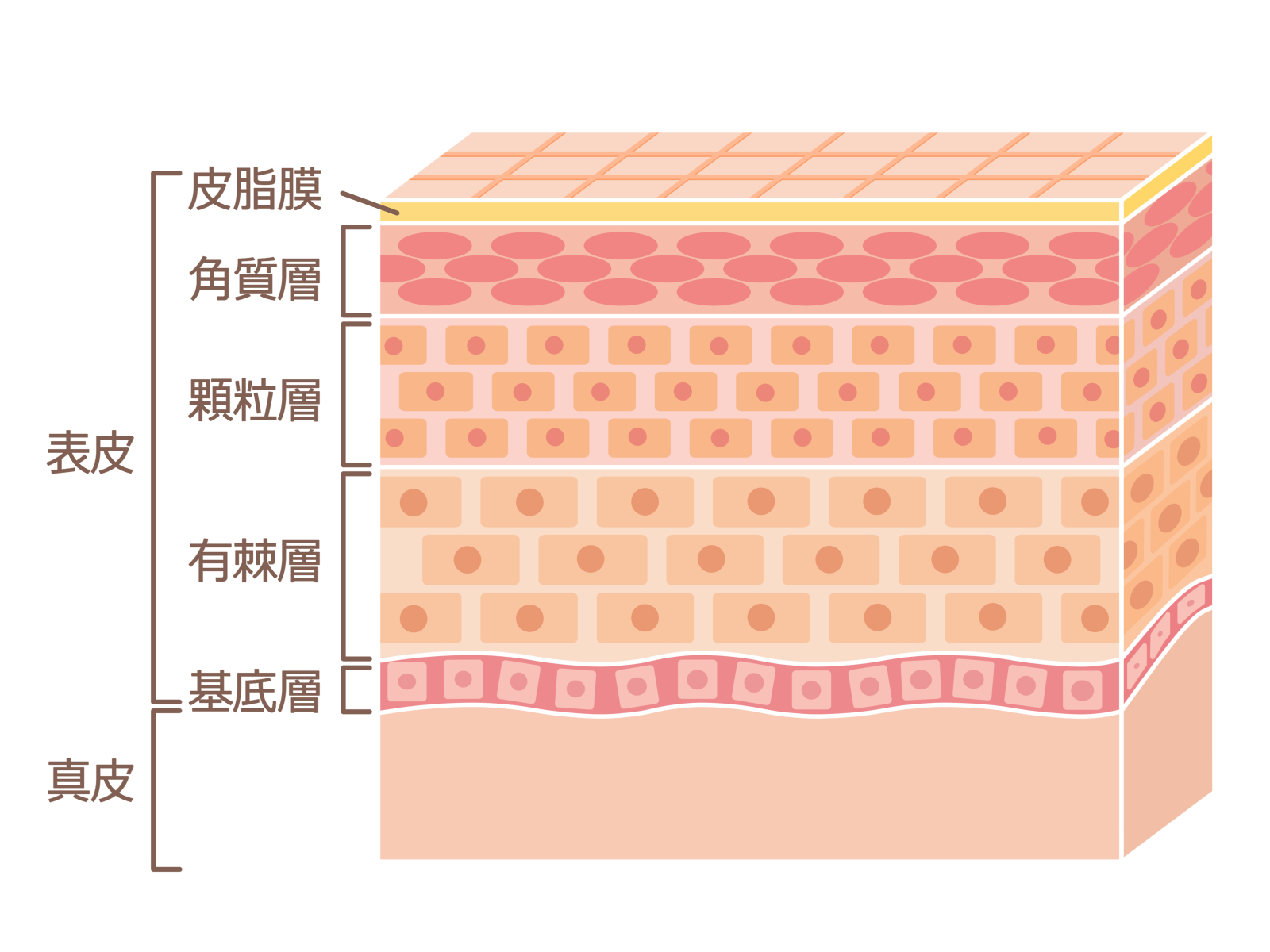1年の中で熱中症対策・紫外線対策が必要な時期となりました。昨今の猛暑は、温度や湿度の変化が激しく、健康維持のためにも、熱中症の対策が必須となります。日頃の食事を見直し、熱中症対策および予防に効果が期待できる食べ物を把握しておきたいものです。
また、日焼け止めや日傘、UVカット機能のある衣類を着用するなど、本格的に紫外線対策をしている方も多いと思います。紫外線量がピークに達したこの時期、紫外線によるダメージから本気で肌を守るのであれば、外側からのUVケアとともに、食べ物による内側からのケアもしなければ悪影響は防げません。
今回は、熱中症の症状や日焼けを軽減し、熱中症および紫外線のダメージから体と肌を守る効果のある栄養素や食べ物についてご紹介いたします。

熱中症とは
熱中症とは、温度や湿度の高い空間に長時間いることにより、体内の水分・塩分などが奪われて、体の熱を逃がすことができず、体温調節機能に異常をきたす症状を指します。
主な症状としては、めまい・気分の悪さ・頭痛・吐き気・倦怠感・手足のしびれ・立ちくらみなどが挙げられます。重症の場合には、意識の喪失や、正常なコミュニケーションが取れないなどの状態となります。
熱中症というと、屋外で発症するイメージがあるかと思いますが、最近では室内で発症する方も増えており、注意が必要です。重症になると、救急搬送が必要になったり、最悪の場合は死亡したりするケースもあります。
熱中症にかかりやすい人とは
熱中症にかかりやすい人としては、子供や高齢者が挙げられます。
子供は、大人に比べると体温調節機能が十分でなく、新陳代謝も活発であるため、水分や塩分を失いやすく、脱水症状なども発症しやすいです。
また、高齢者も体温調節機能に衰えがみられ、汗をかきにくく、熱がこもりやすいので注意が必要です。年齢とともに喉の渇きを感じにくくなるので、水分補給もおろそかにしがちとなります。
成人の方々も、もちろん熱中症には注意しなければなりませんが、子供や高齢者は特に熱中症にかかりやすいことは、基礎知識として知っておきましょう。
窓を開けて風通しを良くし、室内の熱を逃がしたり、エアコン・扇風機を使って室内を適温に保ったりするなど、工夫が必要です。
なお、高齢者の方の中には、暑さを我慢しなければならないという考えをお持ちの方もいらっしゃいますが、現代の夏の暑さは気力でしのげるようなレベルではないため、エアコンなどを無理に切らず、有効に活用することの大切さを忘れないようにしましょう。
熱中症対策になる栄養素を含む食べ物
熱中症の回復や緩和に効果のあるおすすめの食べ物を、栄養素別にご紹介していきます。コンビニなどでも簡単に手に入るものなどを事前に把握しておき、熱中症対策に努めましょう。
・クエン酸を含む食べ物
クエン酸は、疲労回復に効果があるほか、疲労の原因になる乳酸の蓄積を防ぎ、脱水症状を改善するためのミネラルの吸収を助けるはたらきがあります。
また、クエン酸回路と呼ばれる、細胞内のミトコンドリア内でエネルギーを燃やす回路の活動を活発化してくれるので、疲れを感じにくくなります。
梅干し、レモン、酢などを含むものは、クエン酸を多く含有しているので、おすすめの熱中症対策の食べ物です。
・カリウムを含む食べ物
カリウムは、発汗によって塩分とともに失われやすい成分であるため、熱中症対策の際には、積極的に摂りたい栄養素です。細胞の浸透圧を調整する役目があり、体内に蓄積した余分な塩分を排出するはたらきがあります。
カリウム不足になると、熱中症の症状を発症する可能性があるほか、低血圧・食欲不振・不整脈・筋力低下・頻脈といった症状がみられることもあるため、適時補給しましょう。
カリウムは、バナナ・さつまいも・ほうれん草・海藻・豆類・魚類・肉類などの食べ物に含まれていますので、熱中症対策のためにもしっかりと摂りましょう。
・ビタミンB1を含む食べ物
ビタミンB1は、ビタミンB群の中でも、熱中症対策として、特におすすめの栄養素です。糖質からエネルギーを生成するための代謝を助けてくれるほか、脳や神経のはたらきを正常化してくれます。
糖質をエネルギーに変えることで疲労回復効果が見込めるため、ビタミンB1をきちんと摂取することにより、熱中症に負けない態勢を整えることができます。
ビタミンB1は、きのこ類・大豆・玄米・モロヘイヤ・豚肉などの食べ物に含まれているので、熱中症対策のためにも、日々の食事に効率的に取り入れるようにしてみると良いでしょう。
・ビタミンCを含む食べ物
ビタミンCは、体内の酸化の進行を抑える抗酸化作用があるほか、コラーゲンをつくる酵素のはたらきを助ける効果も期待できます。
ビタミンが欠乏してしまうと、全身の疲れや倦怠感を感じやすくなり、コラーゲン不足によって、骨や血管の状態が悪くなる恐れがあります。
レモン・アセロラ・キウイフルーツ・赤色および黄色のピーマン・じゃがいも・さつまいもなどの食べ物に、ビタミンCは多く含まれているため、熱中症対策のためにしっかりと摂るようにしましょう。
紫外線対策に有効な栄養素
ビタミンC
美白効果に優れたビタミンCには、肌を酸化させ、メラニンの生成を促進する活性酸素を抑える抗酸化作用のほか、黒くなったメラニン色素を白色化し、シミやそばかすを防ぐ働きがあります。また、紫外線により破壊されてしまうコラーゲンやエラスチンの生成を助けたり、強い抗酸化作用を持つビタミンEの作用をサポートする働きも。2、3時間で体外に排泄されてしまうので、こまめに摂取することがポイントです。
【ビタミンCを含む食べ物】オレンジ、イチゴ、ブロッコリー、パプリカ、トマト、グレープフルーツ、キウイ、スイカ、カリフラワー、芽キャベツなど
リコピン
日光に対する耐性を上げることができる、赤い野菜や果物に含まれるカロテノイド色素。強い抗酸化作用があり、シミ、そばかすの原因であるメラニンを作る酵素・チロシナーゼの生成を抑える作用があります。ビタミンEと組み合わせて摂ると、より美白効果が期待できます。
【リコピンを含む食べ物】トマト、スイカ、グレープフルーツ、チリパウダーなど
β-カロテン
紫外線から肌を守り、活性酸素を抑え、肌の老化や肌荒れなどを防ぐ効果がある栄養素。チロシナーゼの活性を弱めてメラニン色素の生成を抑制する効果や、皮膚や粘膜を保護し、強くする働きがあります。体内でビタミンAに変わるため「プロビタミンA」とも呼ばれ、皮膚の免疫力の向上など、ビタミンAの効果も期待できます。
【β-カロテンを含む食べ物】にんじん、ほうれん草、かぼちゃなどの緑黄色野菜
ビタミンE
活性酸素が発生すると、細胞膜の代わりに酸化され、活性酸素を無害にできる栄養素。この抗酸化作用により肌の老化を防いだり、血行を良くし、肌のターンオーバーを正常化してメラニン色素の排出などを促します。
【ビタミンEを含む食べ物】ナッツ類、アボカド、キウイ、緑黄色野菜など
亜鉛
紫外線に対する皮膚の抵抗力に関わる栄養素。肌の新陳代謝を活発にし、皮膚を健やかに保つ働きがあります。亜鉛が不足すると、皮膚の抵抗力は弱まります。
【亜鉛を含む食べ物】うなぎなどの魚類、鶏のささみなど肉類、牡蠣、ホタテ、レバーなど
アミノ酸
紫外線が肌に入り込むのを防ぐ効果や、メラニンの生成をコントロールし、シミを防ぐ効果があります。
【アミノ酸を含む食べ物】卵、牛乳、豚肉、牛肉、鶏肉、魚など
オメガ3脂肪酸
抗酸化作用があり、光老化や、日焼けによる痛みや炎症を和らげ肌を守る効果があります。週2回を目安に食事に取り入れることで、必要量を摂取できると言われています。
【オメガ3脂肪酸を含む食べ物】鮭、ニシン、サバ、マス、イワシなど
紫外線対策におすすめの食べ物

トマト
リコピンを多く含むトマトは、夏の旬野菜でもあり、この時期毎日摂りたい食べ物。生で食べるなら、大きなトマトよりリコピン量の多いミニトマトを選びましょう。
また、リコピンは加熱すると増加し、オイルを加えると吸収が高まるので、加熱調理をしたり、良質なオリーブオイルと一緒に食べるとより効果的です。
ピーマン
抗酸化作用があり、美肌に効果的なビタミンACE(ビタミンA、C、E)を豊富に含むピーマン。夏が旬の野菜なので、こちらも積極的に食べたいところです。濃い緑色の野菜には日焼け防止効果や日焼けした肌を修復する作用も期待できます。
パプリカ
赤ピーマン、黄ピーマンとも呼ばれるパプリカは、夏野菜の中でもビタミンCが特に多い食べ物。赤パプリカに含まれている赤い色素成分・カプサンチン*1は、抗酸化力の高い栄養素としても注目されています。
*1…カプサンチン:カロテノイドの一種です。抗酸化作用を持ち、善玉コレステロールを上昇させる働きがあると言われています。
ベリー類
イチゴなどのベリー類の果物に含まれるポリフェノール・エラグ酸は、1831年にフランスで発見され、1996年に美白成分として厚生労働省に認可されている成分。強力な抗酸化作用と、メラニン色素の生成に関わる酵素・チロシナーゼの働きを抑える作用があります。
リンゴ
リンゴの皮のリンゴポリフェノールには様々なポリフェノールが含まれており、相乗効果による高い抗酸化力で活性酸素から肌を守ります。また、メラニン色素の生成を抑制し、シミ防止に効果があるという研究結果も発表されています。
サツマイモ
夏が終わるころ、美白ケアとして食べたいのが秋に旬を迎えるサツマイモ。ビタミンCやビタミンE、β-カロテンを多く含み、UVケア用の化粧品にも使用されている酸化防止効果のある色素が多く含まれています。紫色のサツマイモには抗酸化作用も。
うなぎ
うなぎはビタミンAやビタミンEを多く含む美容食。夏バテ予防や疲労回復にも効果があり、紫外線による目へのダメージケアにもおすすめです。アナゴにも同じ栄養素が含まれているので、うなぎの代わりにアナゴでもOK。

鮭
鮭には日光から肌を守る効果のあるオメガ3脂肪酸や、強い抗酸化作用のあるアスタキサンチンが多く含まれています。週に2回を目安に食べると効果的です。
ココナッツオイル
直接肌に塗ることで日焼け止めとしても効果のあるココナッツオイル。抗酸化作用にも優れています。体質により、合う合わないがあるようですが、摂取量は1日に1/4カップくらいが目安です。
アーモンド
紫外線ダメージから肌を守るフラボノイド・ケルセチンや、抗酸化力が強いビタミンEを多く含みます。毎日20粒のアーモンドを食べるという実験では、同じ量の紫外線を浴びた場合、アーモンドを食べた参加者のほうがアーモンドを食べていない参加者よりも日焼けしにくかったという結果が残っているそうです。
ダークチョコレート
カカオ70%以上のチョコレートには、日焼けに対する耐性を最大25%強める効果があります。摂取量の目安は1日60gくらい。ただし、ミルクチョコレートはミルクにポリフェノールの吸収を抑える作用があるので効果は期待できません。
紫外線対策に効果的な飲み物

緑茶
ビタミンCに加え、強力な抗酸化作用のあるポリフェノール・没食子酸エピガロカテキンが多く含まれています。没食子酸エピガロカテキンは毎日摂取することにより、紫外線による肌の老化を遅らせるだけでなく、皮膚がん予防の効果もあるそうです。1日2杯以上が効果的。
また、抹茶には他の緑茶の3倍の没食子酸エピガロカテキンが含まれています。
ザクロジュース
ザクロにはエラグ酸など強い抗酸化作用のある成分が含まれています。皮膚科専門医によると、日光に対する肌の強さを25%引き上げる効果もあるとか。
ザクロの果実を手に入れるのは難しいので、おすすめはジュース。他の果物と比べると高価なものが多いですが、美肌効果も期待できます。
アセロラジュース
レモンの約17倍のビタミンCやポリフェノール、アントシアニンを含み、活性酸素を体内から除去して肌を守る美肌フルーツです。ビタミンCもポリフェノールも体内に蓄積されないので、摂取しやすいジュースでこまめに飲むのがおすすめ。
コーヒー
ポリフェノールなどの抗酸化成分が多量に含まれているコーヒー。毎日コーヒーを飲む人はシミが少なく、特に1日2杯以上(150ml)飲んでいる人は効果が表れているという研究結果もあります。
ポリフェノールは摂取してから2時間ほどで消えてしまうので、少しずつこまめに飲むのがポイントです。
サプリメント
紫外線ダメージの緩和に効果的な栄養素を食べ物だけでは補えない場合は、サプリメントで効率よく摂取しましょう。おすすめはビタミンA、C、E、B2、亜鉛、セレン(セレニウム)、L-システイン。魚があまり得意ではないという方には、オメガ3脂肪酸が摂取できるフィッシュオイルもおすすめです。
紫外線に弱い食べ物
上記とは逆に、食べることで紫外線によるダメージを促進してしまう食べ物があります。いずれも日光に当たらない時間なら問題ないので、摂取する時間に注意しましょう。
「ソラレン」を含む食べ物
ソラレンとは、紫外線を吸収しやすく、シミやそばかすなどの原因になる野菜や果物に含まれている光毒性のある成分。ビタミンCが豊富な柑橘系の果物など、美肌効果のある食べ物に多く含まれています。
ソラレンは摂取してから2時間前後で体に吸収され、活発化します。その後7時間は体内に留まるので、外出する日の朝食などで食べるのは控え、夕食時などにとり入れましょう。
【ソラレンが含まれる食べ物】オレンジ、グレープフルーツ、レモン、キウイ、アセロラ、きゅうり、パセリ、セロリ、三つ葉、シソなど
アルコール
アルコールを摂取した後に紫外線を浴びると、皮膚が酸化して、血管を拡張して炎症を起こす作用のあるプロスタグランジンEという物質が作られます。そこにアルコールの血管拡張と血行促進の作用が加わることで、皮膚が赤くなったり、水ぶくれなどの炎症を起こしやすくなります。野外で飲酒する際には気をつけましょう。
終わりに
どんなに入念に熱中症対策や紫外線対策をしても、暑さによる水分および塩分の欠乏や、紫外線による肌ダメージを完全に防ぐことはできません。
そこで重要になってくるのが日々の食生活。人間の体は食べた物で作られるというように、熱中症の予防に効果が期待できる食べ物や、抗酸化作用や肌を修復する作用、美白効果のある食べ物を積極的に摂ることにより、熱中症による様々な症状や、紫外線による肌ダメージをある程度、予防・回復することができます。
夏の暑い時期に体調が悪くならないように、日頃から食事に熱中症の予防・回復に効果が見込める食事を取り入れて対策を入念にするほか、日焼けしてしまっても諦めず、効果的な食事で日々のUVケアを心がけましょう。